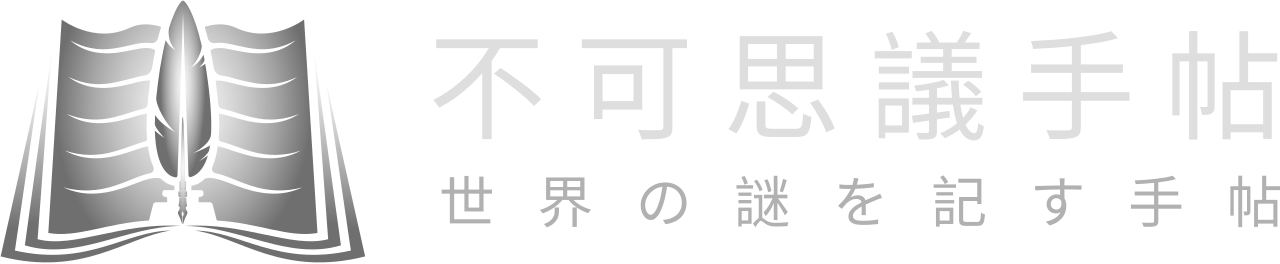ゴビ砂漠に伝わるオルゴイ・コルコイ伝説
モンゴル南部に広がるゴビ砂漠。
焼けつくような日差しと極寒の夜、乾いた大地と吹き荒れる砂嵐。
ここには、今もなお人知の及ばない謎が息づいている。
古くから遊牧民たちの間で語り継がれてきた存在──
それが「オルゴイ・コルコイ」、通称モンゴリアン・デス・ワームだ。
地中を這い、滅多に姿を見せないこの生き物は、
「牛の腸のような形をしている」と言われ、
その周囲では家畜が忽然と消える、という不吉な噂も後を絶たない。
灼熱の砂の海に潜む、正体不明の異形。
それは単なる迷信なのか、それとも──。
1926年、西洋に初めて伝えられた奇妙な存在
1926年、アメリカの探検家ロイ・チャップマン・アンドリュースが、
ゴビ砂漠を横断する探検の途上、現地遊牧民から奇妙な話を聞き取った。
「地中には、赤い巨大な虫のようなものがいる。近づけば命を落とす。」
この伝承は、アンドリュースの著書『On the Trail of Ancient Man』に記録され、
初めて西洋世界に「モンゴリアン・デス・ワーム」の存在が知られることとなった。
アンドリュース自身は慎重な立場を取ったものの、
極限環境に潜む未知生物の可能性を完全に否定することはなかった。
牛の腸に似た生物 報告されるモンゴリアン・デス・ワームの特徴

現地で語られるデスワームの特徴は一貫している。
- 体長は50センチ〜1.5メートル、最大3メートル説も存在
- 色は赤褐色から暗赤色
- 表面は滑らかで、ぬめり光沢を持つ
- 目・耳・口といった明確な器官は見当たらない
普段は砂の下に潜み、活動するのは6〜7月の雨季。
砂の地中を泳ぐように移動する姿は、目撃者たちに強烈な印象を残している。
デスワームは、ただの生き物ではない。
その存在自体が、砂漠に根付いた”恐怖”そのものなのだ。
毒液と電撃 目撃者たちが語る驚くべき能力
モンゴリアン・デス・ワームが特異な存在とされる理由は、
その攻撃能力にある。
黄色い毒液
目撃報告では、デスワームは黄色い霧状の毒液を体から噴出し、
それに触れた生物は皮膚が腐食し、数分以内に命を落とすとされる。
電撃による攻撃
さらに、尾部から高電圧の電撃を放つとも言われる。
デンキウナギのような電気を操る能力を、
乾燥した砂漠環境で持つ生物が存在する可能性は極めて低いとされるが、
報告は後を絶たない。
自然界でこの二重攻撃能力を持つ生物は確認されておらず、
科学者たちの間でも議論は続いている。
灼熱の砂漠を行く 調査隊たちの挑戦と記録

これまでに複数の調査隊が、
この砂の海に潜む謎を追ってゴビ砂漠へと向かった。
1990年代、チェコのイワン・マッカールは、
「ワームチャーミング」と呼ばれる振動誘発技術を用いて生物の誘い出しを試みた。
結果は芳しくなく、マッカールは「幻覚説」にも言及している。
2005年にはイギリスのリチャード・フリーマンらが現地調査を実施。
赤褐色の体が砂中を泳ぐ目撃証言を多数収集したが、
生体サンプルや物理的証拠には依然至らなかった。
灼熱と砂嵐に阻まれ、デスワームはその姿を容易には晒さない。
科学者たちが追うモンゴリアン・デス・ワームの正体
科学界では、いくつかの仮説が提案されてきた。
- 未発見の乾燥地適応型爬虫類説
- 砂漠に適応した新種の電気魚類説
- 過酷な環境下で発生した視覚的・認知的錯覚説
- 伝承文化に起因する複合生物誤認説
いずれも、デスワームの持つとされる毒液・電撃の両能力を、
完全に説明できるものではない。
さらに、ゴビ砂漠は隕石落下の多発地帯でもあり、
地球外由来生物起源説を提唱する研究者も少数存在している。
だが、どの仮説も、決定的な証拠には至っていない。
地中に潜むものを探して 最新技術で迫る砂漠の謎
2025年現在、調査手法は大きく進化している。
赤外線搭載ドローンによる広域監視、
地中探査レーダー(GPR)による地下マッピング、
さらにNASAが開発した極限環境探査ロボットの投入が予定されている。
遊牧民の証言をもとに生息ホットスポットを特定するプロジェクトも進行中であり、
砂漠の地下深くに潜む「未知の生物」へのアプローチが、ようやく現実味を帯び始めている。
今も語り継がれる未解明の存在
科学の光がどれだけ届こうとも、
ゴビ砂漠を旅する遊牧民たちは今もなお、
「砂の下には何かがいる」と信じ続けている。
オルゴイ・コルコイ
モンゴリアン・デス・ワーム
その正体は、未だ明らかになっていない。
だが、それはこの広大な砂の海に、
「人間がまだ知らない世界」が確かに存在することを、静かに物語っている。